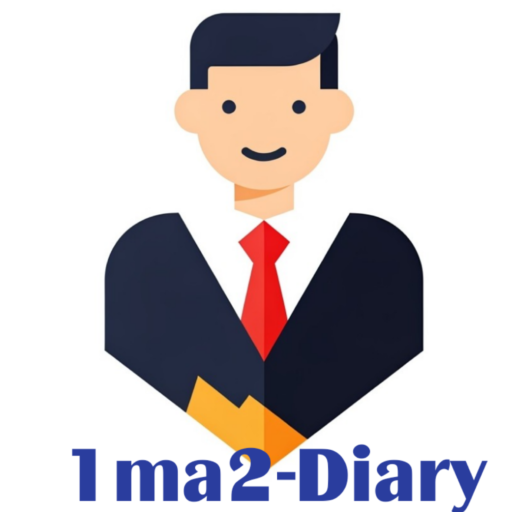【ASD当事者談】「言葉にするのが苦手…」言語化能力が低いと感じる原因と、僕が実践してきた克服トレーニング
前置き
私自身は凹凸さんであり、医学的/カウンセリング的な診断とテスト(AQテスト: 42点等)を経て凹凸さん(ASD)であることを診断されているものです。また、障害者手帳2級を取得しております。また、医師よりADHDである可能性も指摘されております。
しかしながら、私自身はそういった分野の資格を、有しておらず。私自身に診断を行う資格はありません。
また、私は企業法の定義による大企業に在籍しており、係長クラスとして位置付けされています。
自分が行きていくうえで身につけた知識や経験に基づいて記事を執筆しているので、医学的、科学的に矛盾がある場合はご指摘いただければ幸いです。
「うまく言葉にできない」「伝えたいことがまとまらない」
ASD(自閉スペクトラム症)の当事者である僕も、ずっと言語化能力の低さに悩んできました。
あなたも、もしかしたら同じような悩みを抱えて、この記事にたどり着いたのかもしれませんね。
この記事では、僕自身の経験を踏まえながら、ASD当事者が言語化を苦手と感じやすい原因と、僕が社会で生き抜くために実践してきたトレーニング方法についてお話しします。
そもそも「言語化能力」って何だろう?
まず、「言語化能力」とは何か、簡単に整理しておきましょう。言語化能力とは、頭の中にある考えや感情、経験などを、他者に伝わるように言葉(話し言葉や書き言葉)で表現する力のことです。
単に言葉を知っているだけでなく、伝えたい内容を整理する適切な言葉を選ぶ相手に分かりやすいように構成するといった要素が含まれます。
これが苦手だと、コミュニケーションで苦労したり、誤解されたりすることが増えてしまいます。
なぜASDは言語化が苦手と感じやすい?僕が考える2つの原因
ASDの僕が、言語化を特に難しいと感じる主な原因は、大きく分けて2つあると考えています。
原因1:頭の中で「伝えたいこと」を創造するのが難しい
頭の中にモヤモヤとした考えやイメージはあるけれど、それを具体的な言葉に変換して組み立てるプロセスが、とても難しいと感じます。
まるで、設計図なしで複雑な模型を組み立てようとしているような感覚です。「あれも言いたい、これも伝えたい」と思っても、それを順序立てて、相手に理解できる形にまとめるのに非常に時間がかかったり、途中で混乱してしまったりします。
原因2:定型発達者との「認識のズレ」が大きいと自覚しているから
ASDの特性として、物事の捉え方や感じ方が、定型発達の人たちと異なる場合があります。
その『認識のズレ』を自分自身で理解しているからこそ、逆に難しさが増すことがあります。
「どこからどこまで説明すれば、相手に『ちょうどよく』伝わるんだろう?」「この前提は、相手も共有しているだろうか?」「もしかしたら、自分の当たり前は、相手の当たり前じゃないかもしれない…」そんな風に考え始めると、『話すべき内容の「適切な範囲」や「さじ加減」』が全く分からなくなってしまうのです。
「いい感じ」のポイントを見つけるのが、本当に難しい。
諦めないで!言語化能力はトレーニングで伸ばせる可能性
ここまで読むと、「やっぱりASDだと難しいのか…」と落ち込んでしまうかもしれません。
でも、諦めるのはまだ早いです。もちろん、障害の度合いや元々の能力差はあります。定型発達の人と同じように、流暢に、臨機応変に話すことは難しいかもしれません。しかし、トレーニングによって言語化能力を向上させることは可能だと、僕は信じています。
この記事を読んでくださっているあなたは、きっと言語化能力に不安を感じていたり、どうすれば改善できるのか悩んでいたりするのではないでしょうか?そのように課題を認識し、改善しようと思えている時点で、あなたは必ず向上できます。
【実践】僕が社会で生き抜くために続けてきた2つのトレーニング
僕が社会人としてなんとかやってこられたのは、主に以下の2つのトレーニングを意識してきたからです。
トレーニング1:「事前準備」こそ最強の武器!徹底シミュレーション術
定型発達の人のように、その場で即座に考えをまとめて話すのは苦手です。
だから、話すことが予想される場面では、事前に徹底的に準備・シミュレーションします。
・何を伝えたいか(結論)
・なぜそう思うのか(理由・根拠)
・どのような順番で話すか(構成)
・想定される質問と、その回答
これらを、可能な限り具体的に書き出し、頭の中で何度もシミュレーションします。
会議での発言、報告、ちょっとした相談事まで、事前に準備できるものは全て準備する。
これは、定型発達の人が無意識や少ない労力でやっていることを、意識的に、手間をかけて行うということです。
大変ですが、これをやるだけでコミュニケーションの失敗は格段に減らせます。
トレーニング2:「自分と他者の違い」を具体的に把握し続ける
これは、ある意味で一生続ける必要のあるトレーニングかもしれません。
「なぜ、今の自分の説明で相手は疑問に思ったのだろう?」
「定型発達の人は、こういう時どう考える(感じる)傾向があるのだろう?」
「自分のこの表現は、一般的にはどう受け取られるのだろう?」
日々のコミュニケーションの中で生じた疑問やズレを放置せず、「自分と他者(特に定型発達者)の違い」を具体的に分析し、理解しようと努めるのです。
本を読んだり、信頼できる人に聞いたり、時には失敗から学んだりしながら、「他者の視点」や「一般的な感覚」を少しずつ自分の中に蓄積していきます。
これにより、「どこまで話せばいいか」の判断精度を少しずつ上げていくことができます。
おわりに:同じASDでも特性は色々。でも、僕の経験が少しでもヒントになれば嬉しい
ここまで、僕自身の経験に基づいて、ASDと言語化能力についてお話ししてきました。
もちろん、ASDと一言で言っても、特性は本当に人それぞれです。僕の感じている困難さや、効果があったトレーニングが、全ての人に当てはまるとは限りません。
でも、もしあなたが僕と似たような特性を持っていて、言語化に悩んでいるのなら、この記事がほんの少しでも参考になったり、前向きな気持ちになるきっかけになったりすれば、とても嬉しいです。
言語化能力のトレーニングは、一朝一夕に効果が出るものではありません。でも、諦めずに、自分に合ったやり方で少しずつ続けていけば、きっと変化を感じられるはずです。
一緒に、少しずつ前に進んでいきましょう!