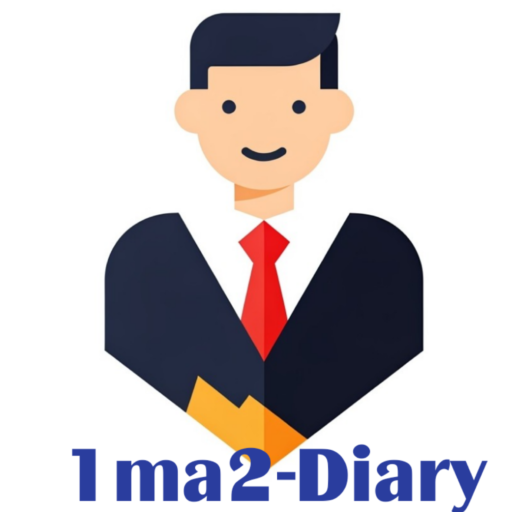【40代ASD・中間管理職が語る】コミュニケーション能力の誤解と真実:「当たり前」が難しい僕なりの生存戦略
こんにちは、一松です。
突然ですが、あなたはコミュニケーション能力に自信はありますか?
そして、そもそも「コミュニケーション能力」とは何だと思いますか?
す「コミュ力」のよくある誤解
「あの人、コミュ力高いよね」
日常でよく聞く言葉です。この場合、多くは「初対面の人とでもすぐに打ち解けられる」「場を盛り上げるのが上手い」といったスキルを指しているように感じます。確かにそれも素晴らしい能力ですが、特にビジネスの世界で重視される「コミュニケーション能力」は、少しニュアンスが異なります。
ビジネスにおける「コミュニケーション能力」の本質
ユーキャンのサイトでは、コミュニケーション能力を次のように定義しています。
コミュニケーション能力とは『対人における意思疎通や協調に必要な力です。』
(出典:ユーキャン 人事担当者お役立ちコラム)
ここでのポイントは「意思疎通」、つまり相互理解です。単に話が上手い、面白いということではなく、
- あなたが思うことを相手に的確に伝えられるか。(発信力)
- 相手が思うことを自分がしっかり受け止められるか。(受信力)
この双方向のやり取りがスムーズに行えることが、本質的なコミュニケーション能力と言えるでしょう。
「伝える」ことの難しさ:私が意識する4つのステップ
これ、簡単そうに聞こえますが、私にとっては非常に難しいことです。特に、情報を「伝える」際には、無意識にはできず、常に以下の4つのステップを意識的に実行しています。
- 伝えたいことの明確化・具体化:まず、自分が何を伝えたいのか、自分自身が具体的に把握している必要があります。自分の中でさえ曖昧なことは、どんな達人でも相手に伝えることはできません。「何を」「どのように」伝えたいのかを明確にすることが大前提です。
- 相手の理解度の把握(相手目線に立つ):次に、伝える相手がそのテーマについて、どの程度の知識や理解を持っているかを把握します。ここがズレていると、いくら正確な言葉を選んだつもりでも、相手には全く伝わりません。専門用語を避けたり、前提知識を補ったりと、相手のレベルに目線を合わせることが重要です。
- 相手にわかる言葉で伝える(具体性の重視):いよいよ伝えるフェーズです。ここで最も重要なのは、「相手が知っている具体的な言葉で伝える」ことです。例えば、「いい感じにしといて」のような感覚的な言葉や抽象的な表現は避けます。なぜなら、自分と相手では、その言葉から連想する経験やイメージが全く異なる可能性があるからです。「良い感じ」の定義が、人によって全く違うのは当然ですよね。できる限り、誰が聞いても同じように解釈できる明確な言葉を選びます。
- 伝わったかの確認と修正:ここまで丁寧に行ったとしても、認識のズレは起こり得ます。そのため、伝えた内容が相手に正しく理解されたかを確認する作業が不可欠です。別の角度から問いかけたり、相手に要約してもらったりします。もし想定と違う反応があれば、それは誤解が生じているサイン。必要に応じてステップ1〜3に戻り、伝え方を修正します。
「受け取る」際も同じプロセスが必要
情報を「受け取る」際も、実は同様の注意が必要です。なぜなら、上記の4ステップを踏んで、正確に情報を発信してくれる人は、残念ながらそう多くないからです。相手の言葉の意図や、曖昧な表現の真意を汲み取るためには、「これはどういう意味ですか?」「〇〇ということでしょうか?」といった能動的な質問や確認を通じて、発信時に気をつける4つのプロセスを、受け手側として行う必要があります。この人が言いたいことはどんなことだろう?「そもそも認識が同じレベルで共有できているのか?」そんな事を話を聞きながら焦点をくっきり合わせていく行為が必要です。
なぜ、私がここまで「当たり前」にこだわるのか? – ASDとカモフラージュ
ここまで読んで、「そんなの当たり前のことじゃないか」「プレゼンテーションの基本だろう」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
私がこれを単なる「プレゼン術」ではなく、「コミュニケーション能力」として、しかもこれほど詳細に書いたのには理由があります。それは、『ASD(自閉スペクトラム症)』の特性を持つ私にとって、この「当たり前」に見えるステップを無意識に、スムーズに行うことが極めて困難だからです。
特別なプレゼン場面だけではありません。家族との日常会話、友人との雑談、職場での報告・連絡・相談といった、普段のあらゆるコミュニケーションにおいて、私は常にこの1〜4をフル回転で意識し、実行しています。
これを怠ると、途端に会話が成り立たなくなり、「空気が読めない人」「話が通じない、おかしい人」と周囲から認識されてしまう。過去にそうした経験からコミュニティ内で不利益を被り、深く傷ついた経験があるからこそ、自分を守るために、無意識のうちに過剰な精神的負荷をかけてでも「普通」を装うのです。
これが、発達障害の分野で「カモフラージュ」あるいは「過剰適応」と呼ばれる状態の中身です。
「周りにどう思われてもいいじゃないか」という意見もあるでしょうし、そう思える方はそれで良いのです。しかし、私にとって、このカモフラージュは、社会で生きていくために身につけざるを得なかった生存戦略であり、やめようと思って簡単にやめられるものではありません。こういった経験をされたことがある人が多いので、ASD当事者は、常に神経をすり減らし、二次障害として精神疾患を発症しやすいと言われるのです。
(ちなみに、かかりつけ医からは、むしろASDの特性が強く「我を通す」タイプの人の方が、周りからは「癖が強い」と思われても本人はあまり病むことがない。周囲に合わせようと無意識にカモフラージュを行いやすい、特性のグラデーションが薄い(ように見える)人の方が、精神的な負荷を溜め込みやすい傾向がある、とも聞きました。)
心当たりのあるあなたへ
もし、この記事を読んで「自分にも心当たりがある」「いつも頑張りすぎているかも」と感じた方がいらっしゃったら。
カモフラージュを今すぐやめる必要はありません。おそらくそれは、長年かけて身につけた、あなたにとってのアイデンティティの一部であり、社会でうまくやっていくための大事なスキルになっているはずだからです。
ただ、どうか覚えておいてください。その頑張りは、確実にあなたの神経をすり減らす行為であるということです。
「自分はコミュニケーションのために、人一倍エネルギーを使っているんだ」
この事実に気づいているだけで、万が一、心が不調になったときに、早期回復への大切な手がかりになるかもしれません。
私自身、この過剰適応が原因の一つとなり、精神疾患で休職することになりました。休職中に「カモフラージュ」という概念を知り、自分のこれまでの生きづらさや疲労感の正体を自覚したことが、回復と、自分を再構築していく上での大きな転機となりました。
この記事が、コミュニケーションに難しさを感じている方、ASD当事者の方、そしてその周りの方々にとって、少しでも何かのヒントや、自分を理解するための一助となれば幸いです。