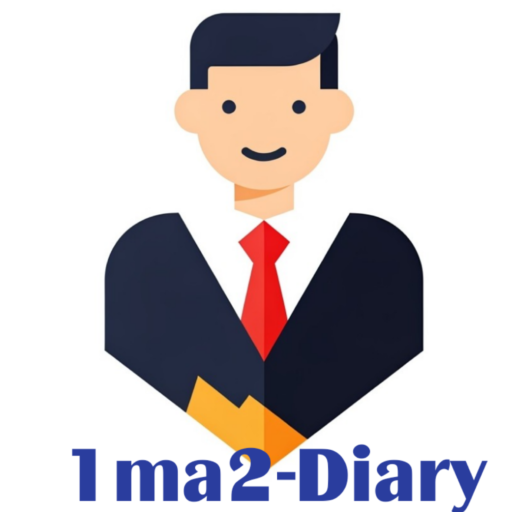「若手が育たない」は本当? 変化の時代に求められる新入社員教育と技術継承のリアル
はじめに
「最近、新入社員の教育が難しくなった…」
「若手がなかなか育たない…」
多くの企業で、このような声が聞かれるようになりました。かつては、OJT(On-the-Job Training)を通じて現場で経験を積み、時間をかけて一人前の技術者や担当者を育てていくのが日本の企業の人材育成モデルでした。しかし、現代のビジネス環境下では、難しくなってきています。
本記事では、なぜ新入社員教育が難しくなっているのか、その背景にある要因を探り、将来にわたって企業が持続的に成長していくために、今、私たちが向き合うべき若手育成の本質について考えていきます。
なぜ新入社員教育は難しくなったのか?
1. 働き方改革と効率化の波
現代は、働き方改革による労働時間短縮や、生産性向上が強く求められる時代です。限られた時間の中で成果を出すことが優先され、新人につきっきりで指導したり、試行錯誤を見守ったりする時間的・精神的な余裕が現場から失われつつあります。効率化の名の下に、教育という時間のかかるプロセスが後回しにされがちなのです。
2. 不況とリスク回避志向の高まり
経済の先行き不透明感や不況の影響も無視できません。特に、数年単位、数百人規模で動くような大規模開発プロジェクトは、企業にとって大きなリスクを伴います。かつては、このような大きなプロジェクトが若手にとって絶好の成長機会となっていましたが、失敗のリスクを恐れるあまり、挑戦的な経験を積ませる場そのものが減少しています。
さらに、短期的な利益を最大化し、株主への還元を優先する社会全体の流れも、長期的な視点での人材育成投資を抑制する要因となっています。
3. 市場変化への対応とリソース配分の変化
市場の変化は激しく、企業は常に新しい技術やビジネスモデルへの適応を迫られています。その結果、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ)は、目先の変化に対応するために費やされがちです。
その結果、社内の人材育成に十分なリソースを割けなくなり、内部での育成が追いつかない部分を、即戦力となる社外からの人材採用で補う動きが加速しています。これは短期的な課題解決には有効ですが、長期的な視点で見ると、自社独自の文化や技術継承を難しくしています。
派遣に頼るということも同じ現象を生み出します。
「疑似体験」では得られない、リアルな経験の価値
こうした状況に対し、「疑似体験を通じて成功体験を積ませれば良い」という方針を打ち出す企業もあります。シミュレーションや研修プログラムはもちろん重要ですが、それだけでは真の成長には限界があります。
なぜなら、実際の業務には、
- 予期せぬイレギュラーな問題の発生
- 大きな金額や多くの人が関わることによるプレッシャーや緊張感
- 多様な関係者との複雑なコミュニケーション
といった、教科書通りにはいかない要素が満ち溢れているからです。これらは、安全な環境下での疑似体験では決して得られません。ヒリヒリするような緊張感の中で問題を乗り越えたり、予期せぬトラブルに機転を利かせて対応したりといった『本当の経験』こそが、人を大きく成長させるのです。
また、疑似体験の中で無理なストレスをかけようとすれば、ハラスメント問題に繋がりかねません。
短期的な利益と、未来への種まき
現有のリソースを最大限活用し、新たな投資(特に時間のかかる人材育成)を抑制すれば、短期的には企業の利益は最大化されるかもしれません。しかし、それは未来に向けた種まきを怠っていることに他なりません。
10年後、20年後も企業が第一線で戦い続けるためには、その時代を担う人材が必要です。今、若手に「本当の経験」を積ませ、技術やノウハウを継承していかなければ、企業の将来はじりじりと先細りしていくことは自明の理です。
未来のために、今できること
私自身、この先まだ20年は今の会社で働くつもりです。だからこそ、会社が将来も持続的に成長し、安心して働き続けられる環境であってほしいと願っています。そのためには、10年後、20年後に第一線で活躍できる技術者やリーダーを、今から育てていく必要があります。
疑似体験に頼るだけでなく、どうすれば若手に「本当の経験」を積ませ、確かなスキルと自信を身につけてもらえるか。リスク管理をしつつも、挑戦できる機会をいかに創出するか。経営層が見えていないかもしれない問題には、将来の当事者が声を上げなければいけないと思います。
まとめ
新入社員教育の難易度が上がっているのは事実です。しかし、「難しいから仕方ない」と諦めるのではなく、変化する環境の中で、いかにして未来を担う人材を育てていくか、その方法を模索し続けることが重要です。
若手への投資は、単なるコストではありません。企業の未来を創るための、最も重要な「種まき」なのです。