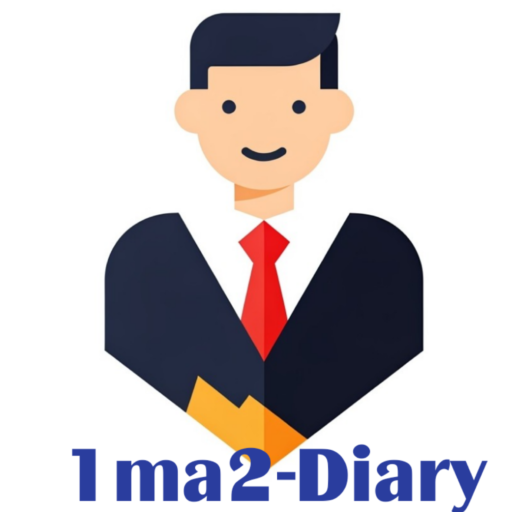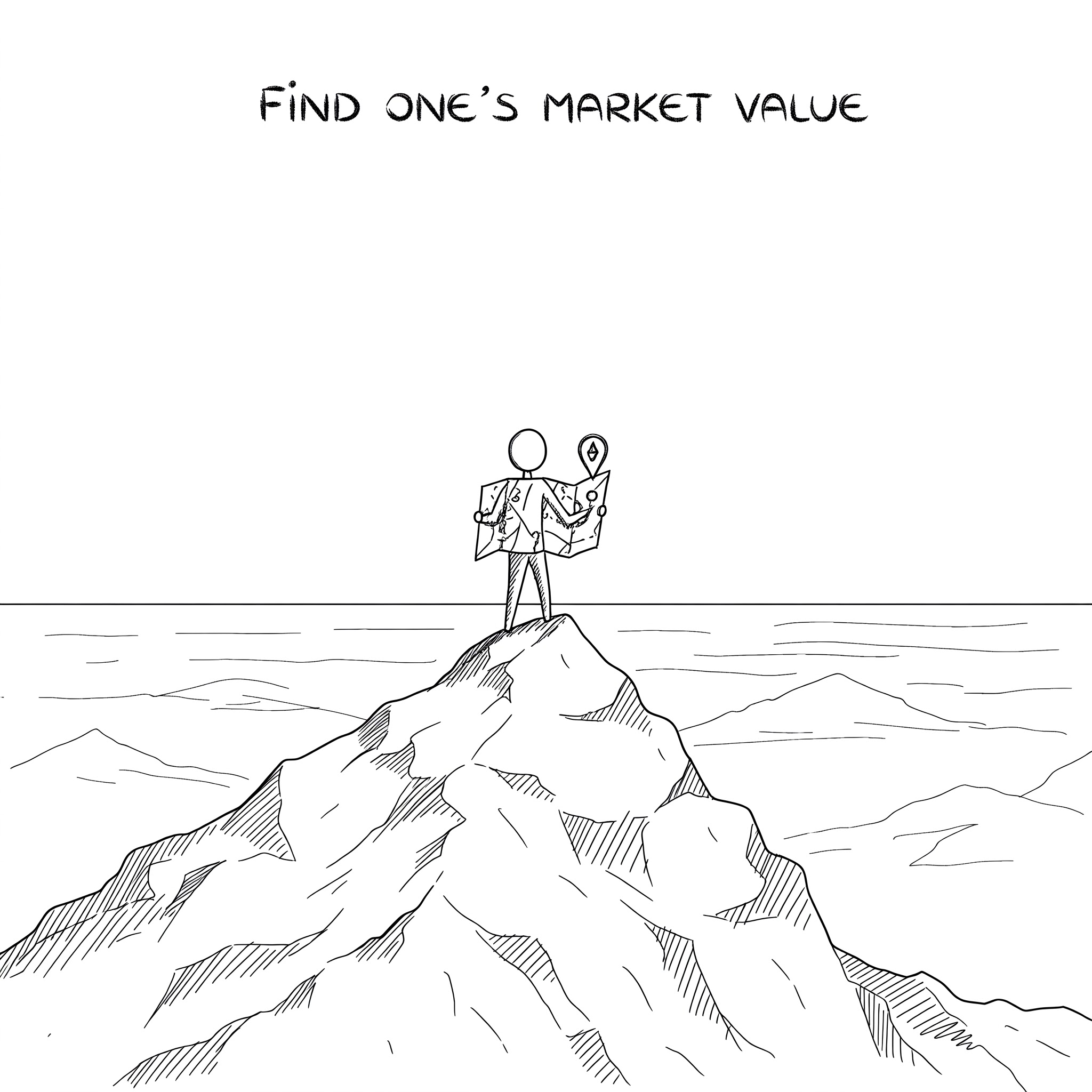業務効率改善コンサルは本当に必要?大手企業が陥る罠
企業の成長や競争力維持のために「業務効率改善」は永遠のテーマです。そして、その解決策として「コンサルタント」の導入を検討する企業も少なくありません。
世の中には、経営戦略、IT、人事、そして業務効率改善など、様々な分野のコンサルタントが存在します。私自身、これまでの仕事で複数の「業務効率改善コンサルタント」と呼ばれる方々と関わってきました。
しかし、私の経験上、残念ながら「コンサルタントを入れたことで、現場の業務効率が目に見えて改善された」という経験は一度もありませんでした。
もちろん、これはあくまで私の個人的な経験に基づく意見です。コンサルタントという職業や、すべてのコンサルティングサービスを否定するつもりは全くありません。
今回は、私の実体験を踏まえ、特に「業務効率改善コンサルタント」の必要性について、特に大手企業におけるメリット・デメリット、そしてより効果的だと考える改善策についてお話ししたいと思います。
コンサルタントが必要となるケースとは?
まず、大前提として、コンサルタントが有効な場面も確実に存在します。
- 会社設立直後: 何から手をつけて良いか分からず、事業プロセス構築の指針が欲しい場合。
- 新規事業・新規プロセスの導入時: 社内に知見やノウハウがなく、外部の専門的な知識や客観的な視点が必要な場合。
このような、社内に知見が不足しており、外部の専門家のサポートが明確に必要な状況においては、コンサルタントの導入は有効な選択肢となり得ます。
大手企業における「業務効率改善コンサル」導入の現実
一方で、既にある程度の業務プロセスが確立されている大手企業にとって、外部の業務効率改善コンサルタントを導入することは、メリットよりもデメリットの方が大きいのではないか、というのが私の考えです。
その最大の理由は「企業風土」です。
北海道でサトウキビが育たない様に、長年培われてきた企業独自の文化や慣習、従業員の価値観といった「風土」に合わない、一般化されたプロセスやツールを導入しても、結局は根付かず、形骸化してしまうケースが多いのが自分の経験です。
コンサルタントは、様々な企業の事例やベストプラクティスを基に提案を行いますが、それが必ずしもその企業の「土壌」に合うとは限りません。むしろ、既存のやり方を否定され、新しいやり方を強制されることで、現場の混乱を招き、従業員のモチベーションを低下させてしまう事すらありました。
それでも大企業に導入される業務効率改善系コンサル
では、なぜ大手企業でも業務効率改善コンサルタントが導入されるのでしょうか?
皮肉な見方かもしれませんが、導入を推進した経営層や幹部にとって「外部の専門家を入れて、これだけの改善活動を行った」という分かりやすい『成果』(報告書や提案資料など)が得られることは、メリットと言えるのかもしれません。体外的なアピールや、社内での自身の評価につながる可能性はあります。
しかし、その裏側で、現場は「コンサルタントへの説明」「資料作成」「新しい(そして多くの場合、現場の実態に合わない)ツールの操作」といった、本来の業務ではないタスクに忙殺され、疲弊していきます。
「みんなでタスクを見える化しましょう!」「ボトルネックを発見して、潰しましょう!」
コンサルタントから、このような言葉を何度聞いたことでしょう。手法自体は間違っていないのかもしれません。しかし、「見える化」や「共有」のために費やす膨大な工数に見合うだけの効果が、果たして得られているのでしょうか? 私の経験では、その工数を投入した結果、プラスになった試しがありません。
コンサルに頼る前に試すべき、より効果的な改善策
では、どうすれば本当に業務効率を改善できるのでしょうか? 外部のコンサルタントに頼る前に、企業内部でできること、やるべきことがあるはずです。
- 生え抜きの幹部・社員の知見を活かす環境を作る: その会社、その部署のことを一番よく知っているのは、長年そこで働いてきた生え抜きの幹部や従業員です。彼ら・彼女らが自身の経験や課題意識に基づき、「もっとこうすれば良くなる」というアイデアを出し、実行できる環境を整えることが重要です。トップダウンだけでなく、ボトムアップの改善活動を奨励し、サポートする体制が、より良い効率をもたらしてくれるのではないでしょうか?
- ボトルネックを知る有識者による「OJT」の実施: 多くの場合、業務のボトルネック(滞留箇所)や非効率な点は、現場の有識者(ベテラン社員など)は既に把握しています。その有識者が、関係するメンバーに対して直接指導・教育(OJT)を行う方が、よほど実践的で効果的な改善につながる事も多いです。OJTは決して新人教育だけのものではありません。中堅・ベテラン社員への再教育や、部署間の連携強化にも活用できます。
- ボトルネック解消を評価する「人事制度」: 日々の業務の中で、非効率な点に気づき、自ら改善策を考え、実行した従業員を正当に評価し、報いる人事制度を導入することも有効です。改善へのインセンティブが働くことで、従業員の当事者意識を高め、自律的な改善活動を促進することができます。
最後に:良いコンサルタントをご存知でしたら教えてください
ここまで、私の経験に基づき、業務効率改善コンサルタントに対してやや否定的な意見を述べてきました。
もしかしたら、単に私がこれまで「素晴らしい業務効率改善コンサルタント」に出会う幸運に恵まれなかっただけなのかもしれません。
世の中には、本当にクライアント企業のことを考え、現場に寄り添い、持続可能な改善を実現してくれる素晴らしいコンサルタントや、非常に評判の良いサービスを提供している会社も存在するのだと思います。
もし、読者の皆様の中で「ここの業務効率改善コンサルは本当にすごかった!」「このサービスは効果があった!」という経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントなどで教えていただけると嬉しいです。
この記事が、業務効率改善やコンサルタント導入を検討されている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。