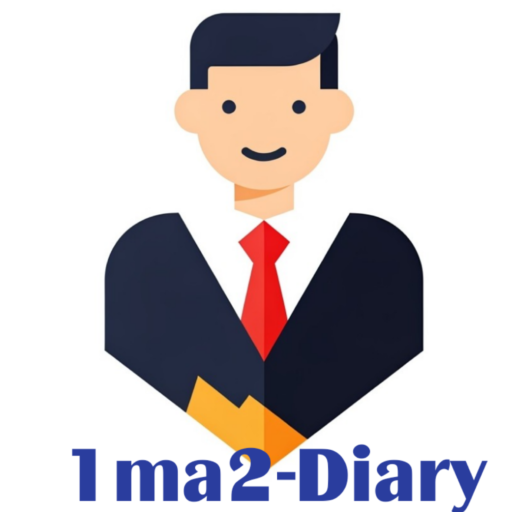「合理的配慮」の理想と現実:ASD/ADHD当事者が語る、職場での難しさと未来への希望
こんにちは、一松です。僕はASD(自閉スペクトラム症)の特性が強く、ADHD(注意欠如・多動症)も併せ持っています。
今回は、いわゆる合理的配慮について今思っていることをつらつらと書いてみたいと思います。
はじめに
診断を受けた時、正直、ほっとしたんです。「肩の荷が下りた」という表現がぴったりでした。これまでずっと「なんで自分はこんなに辛いんだろう」「周りと違うんだろう」と感じてきたこと。それは、僕のせいではなく、持って生まれた特性によるものだった。「辛いと感じていいんだ」と、初めて公に認めてもらえたような気がして、少しだけ心が軽くなりました。
「合理的配慮」という言葉の浸透と、現場の戸惑い
最近、「合理的配慮」という言葉をよく耳にするようになりました。障害者差別解消法の改正もあり、社会全体で障害のある人への配慮意識が高まっているのを感じます。
僕自身、以前に体調を崩して休職し、その後復職した経験があります。その際、カウンセラーさんや産業医の先生が、職場に対して「合理的配慮」を意識してもらえるよう、丁寧に働きかけてくれました。本当にありがたいことでした。
ただ、一方で、「言葉」は急速に浸透しているけれど、実際の現場では「具体的にどうすればいいのか?」という戸惑いが広がっているようにも感じています。
「どうしてほしい?」と聞かれても…当事者のジレンマ
復職後、上司は僕に「どんな働き方がやりやすい?」「何か配慮してほしいことはある?」と、とても親身になってヒアリングしてくれました。その気持ちは本当に嬉しかったのですが、正直、僕は困ってしまいました。
なぜなら、僕自身が「どうすれば働きやすくなるのか」を明確に言葉にできなかったからです。
- 自分が何に困っているのか、漠然とはわかっても、それを具体的な要望として伝えるのが難しい。
- そもそも、定型発達の方々が「普通」にできていることと、僕が困難を感じることの「差」を、うまく言語化できない。
非定型発達の当事者としての本音を言えば、「そこを“汲んで”ほしい」と思ってしまうんです。言葉にしなくても、僕の特性を理解して、必要なサポートを自然に提供してほしい、と。
汲み取る側の難しさ – 職場のジレンマ
でも、少し冷静になって職場の立場から考えてみると、それがいかに難しい要求かも理解できます。
- 僕以上に僕のことを理解している人はいないはずなのに、その本人が「わからない」と言っているのに、周りがどうやって的確な配慮をできるだろうか?
- 「特性は人それぞれ違うから、本人に合わせて配慮して」と言われても、具体的に何をどうすればいいのか、判断するのは非常に難しい。 下手に配慮したつもりが、逆に本人の負担になったり、他の従業員との間に不公平感を生んだりする可能性だってある。
僕がもし上司の立場だったら、「そんなこと言われても、どうしようもないよ…」と途方に暮れてしまうかもしれません。
「合理的配慮」って、言葉にするのは簡単です。でも、根底には「分かり合えない」という現実があるからこそ、配慮が必要になる。その「分かり合えない」者同士が、お互いを理解し、適切な配慮を見つけ出すのは、本当に骨の折れるプロセスなのだと痛感しています。だからこそ、そこに歪みが生まれてしまう状況があるのだと思います。
それでも、未来への希望はある
ここまで、合理的配慮の難しさについて語ってきました。でも、決して悲観しているわけではありません。
僕が子どもの頃、20年、30年前と比べたら、発達障害に対する社会の理解や受容度は、間違いなく大きく進歩しました。「変わった子」「困った子」で片付けられていたかもしれない僕のような存在が、今は「特性」として認識され、支援の対象と考えられるようになった。これは、本当に大きな変化です。
今の課題は、その「理解」や「受容」を、具体的な「アクション」にどう繋げていくか、その方法論がまだ確立されていない点にあるのだと思います。
お互いを尊重し、歩み寄れる社会へ
理想を言えば、
- お互いの違いを認め、尊重し合うこと。
- 一方的に配慮を求める/求められるのではなく、お互いに歩み寄ろうとすること。
- 時には、お互いに譲り合うこと。
そんな関係性を、職場だけでなく、社会全体で築いていくことができれば、僕のような発達障害の当事者だけでなく、誰もがもっと「生きやすい」と感じられる社会になるのではないでしょうか。
合理的配慮の実現は、簡単な道のりではありません。当事者も、周囲の人々も、試行錯誤しながら、時にはぶつかり合いながら、少しずつ理解を深めていくしかないのだと思います。
それでも、諦めずにコミュニケーションを取り続け、お互いを尊重する気持ちを持ち続けること。それが、より良い未来への第一歩だと信じています。
この記事が、同じような悩みを抱える方や、合理的配慮について考えている方にとって、何か少しでも考えるきっかけになれば幸いです。