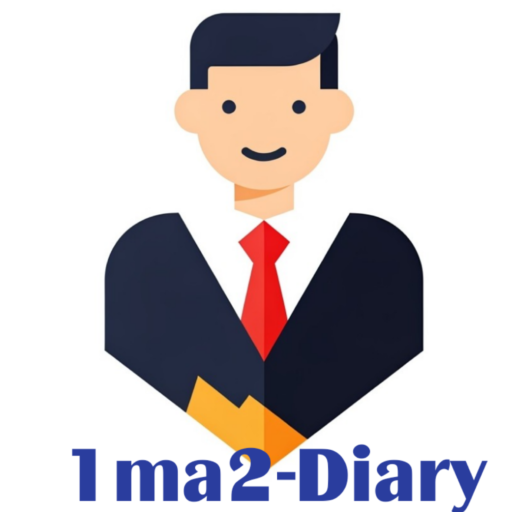【メカ設計】「原因不明」の「初歩的な」不具合が繰り返されるのか?現場を疲弊させる悪循環
はじめに
「〇〇プロジェクトで原因不明の不具合が発生した!悪いけど、ちょっと力を貸してくれないか?」
最近、こんな飛び込みの業務依頼が増えていませんか? 設計者や技術者の方なら、一度は経験があるかもしれません。しかし、詳しく話を聞いてみると、「原因不明」どころか、設計の基本とも言える部分が見落とされているケースが後を絶ちません。この記事では、なぜこのような事態が頻発するのか、その背景にある構造的な問題と、技術現場が陥りがちな悪循環について考察します。
「原因不明」ではない、当たり前の設計ミス
先日も、こんな相談がありました。「歯車の減速比を変えたら、軸受けが想定より早く壊れてしまった。原因がよくわからないんだ。」
メカ設計に携わる方なら、この時点で「ああ、あれか」とピンと来るかもしれません。少し想像してみてください。
…そうです。『減速比を変えれば、当然、軸にかかるトルクは変化します。』トルクが変われば、軸受けにかかる荷重も変わる。そして、荷重が変われば、軸受けの寿命が変わるのは自明の理です。
決して特殊なことではなく、設計の初期段階で検討されてしかるべき項目です。しかし、このような基礎的な見落としによるトラブルが、残念ながら私の身の回りの技術現場にはありふれています。
なぜ基本的なミスが繰り返されるのか? 繰り返される悪循環の正体
問題の根は、単なる個人のスキル不足だけではありません。より深く掘り下げてみると、組織的な課題が見えてきます。
- 担当者の経験不足・知識不足: 基礎的な知識や経験が不足しているため、リスクを予見できず、考慮漏れが発生する。
- 管理職の多忙によるレビュー・教育不足: 本来、設計レビュー(検図)で防げたはずのミスも、管理職が多忙すぎるために十分なチェックが機能していない。若手への教育に時間を割く余裕もない。
- 経営層の的外れな対策: 現場の状況を見た経営層は、「コミュニケーション不足だ」「エンゲージメントが低い」と判断し、研修や対話の機会を増やす施策を打ち出す。
- さらなる現場の負担増: 結果として、ただでさえ忙しい管理職の業務がさらに増え、本来注力すべき設計レビューや若手育成の時間はますます削られる。チーム全体のパフォーマンスは低下。
- 中堅・ベテラン頼みの「火消し」: 結局、問題が発生すると、本来ならより上流の工程や次世代育成を担うべき中堅以降の技術者が突発対応に駆り出され、「火消し」に奔走する。
この負のスパイラルが、もう何十年も繰り返されているように感じます。結果として、組織全体の技術力は底上げされず、むしろ徐々に低下しているのではないでしょうか。
「火消し」に追われる中堅技術者 – それで未来はあるのか?
緊急事態に対応できる経験豊富な技術者は、組織にとって貴重な存在です。しかし、彼らを常に現場の尻拭いに投入していては、組織の成長はありません。
彼ら中堅・ベテラン技術者は、本来、培ってきた経験と知識を活かし、
- 若手を指導・育成するメンター
- より複雑なシステム設計や技術戦略を担うリーダー
- 現場と経営層をつなぐ管理職
といった役割を果たすべきです。目先のトラブル対応ばかりさせていては、彼らが本来持つポテンシャルを潰してしまいます。「今」を乗り切ることばかりに目を向け、将来への投資を怠っていると言わざるを得ません。
短期的な視点から脱却し、未来のリスクに備える
「今、目の前にある問題」への対処はもちろん重要です。しかし、それと同時に、「このまま進んだ場合に将来的に顕在化するリスク」も天秤にかける必要があります。
- 短期的な視点:目の前のトラブルを解決する(中堅を投入して火消し)
- 長期的な視点:若手の技術力不足が将来、より大きな問題を引き起こすリスクを認識し、今から対策を打つ(教育、経験の機会創出)
目先の効率やコストだけを追うのではなく、5年後、10年後の組織の技術力を見据えた判断が求められています。
失敗こそが技術者を育てる – 若手に「泥臭い経験」を
メカ設計の技術力は、座学や綺麗な資料だけで身につくものではありません。教科書通りにいかない現実に直面し、悩み、試行錯誤し、時には失敗し、その原因を徹底的に追求する中で、血肉となっていくものです。
他人の成功体験や失敗談を聞くだけの「疑似体験」では、本当の意味での技術力は身につきません。自分が汗水垂らし、泥をすすって、壁を乗り越えた経験こそが、技術者を大きく成長させます。
もし本当に若手にチャレンジさせたいのであれば、キラキラした華やかなテーマだけでなく、一見地味で泥臭い課題を与え、それをなんとか製品として形にする、という経験を積ませてあげるべきではないでしょうか。それこそが、将来の組織を支える、本物の技術者を育てる道だと信じています。
まとめ
「原因不明」と片付けられがちな設計トラブルの裏には、経験不足、教育不足、管理職の負担増、的外れな経営判断、そして中堅技術者の疲弊という悪循環が存在します。このサイクルを断ち切るためには、短期的な問題解決に追われるだけでなく、長期的な視点に立ち、若手技術者が『失敗から学べる「泥臭い経験」』を積める環境を意図的に作っていく必要があります。
目先の火消しにリソースを割き続けるのか、未来への投資として若手の育成に注力するのか。今、組織全体で真剣に考えるべき時です。