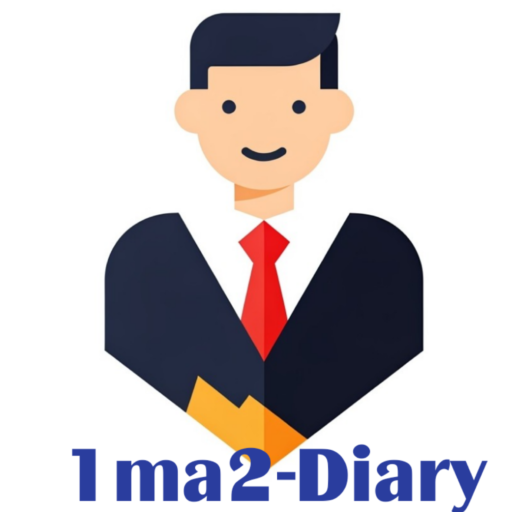変化の時代
卒業のシーズン
我が家には子供が2人。そのうちの1人が先日今年中学校を卒業しました。
卒業式に親として出席してきましたが、我々の頃と全く変わりがないですね。
・国歌演奏
・校長の挨拶
・卒業証書授与
・PTAなどからの挨拶
・送辞
・答辞
なんで三十年近く経っても変わらないんでしょう?
何か劇的に変わっててもいいと思うんですが。
大好きな答辞の一節
答辞で思い出しましたが昔少年ジャンプで連載されていた森田まさのり先生の『ろくでなしBLUES』の登場人物の一人、輪島倍達の答辞の一節が大好きです。
友達や先生や家族…今まで出会った人全ての人々に感謝したい
人生に悔いを残すな だから精一杯やるだけの事はやれ
他人に頼ってばかりじゃいけないが必ずどこかに信じ合える仲間がいる大いに助けあって生きろ
俺はこの六年間で…人間として何よりも大きな事を学んだ
年くった分出おくれたなんて思っちゃいない
ここで得た物を今後の人生にいかに活かすかだ
引用元『ろくでなしBLUES』
この言葉、今でも大好きです。経験は何よりも宝。スタートに遅すぎるってことはない。
これは何歳になっても変わらないですね。
最近の訓示の共通点
さて、最近子供のイベントに出ると必ず出てくるキーワードがあります。それは
『変化の時代です。君たちは、その困難な時代を生き抜いていかなければなりません。』
もうね、聞き飽きました。飽き飽きです。何に飽きたって、その中身に具体性がないんです。
私自身は仕事柄、先端技術や規制動向、政治や経済動向を見ています。なので、AIの進歩で先週最新だったものが今週は古くなっている。なんてものもあり、ヒシヒシと体感します。
が、です。
三十年近く同じ卒業式を運営している側からして、何を変化と捉えているのでしょう?
印鑑が卒業記念品に適さなくなった。位の印象でしか無いのではないか?と感じてしまいます。
子どもたちの目線では
むしろ、子どもたちにとってはどう映っているのでしょうか。
多感な時期を『コロナ禍』とともに過ごし、何が当たり前なのかを知る以前から、変化がともにあったはずです。
我が子はそんな子供時代の生活を『残念』とも『辛い』とも形容せずに、『当たり前』と捉えていました。
変化があるのが当たり前。それが今の若者のスタンダードなのです。
新入社員にも聞いてみた
先日、会社の飲み会で入社1年目の子と会話する機会がありました。
彼は入学すぐにコロナ禍に突入し、飲み会というものをほぼ経験せずに会社に入ったそうです。
また、彼は特殊な学校に行っていたので入社まで時間があったため、スキルアップの為に別の会社で修行を積んできたとのこと。
期間限定で自分の能力を上げたいということを相手方にプレゼンし、受け入れてもらい、実力を少しでも上げて入社してきたのです。
新卒一括採用たった我々の時代には考えもつかない行動でした。
彼らの世代は、身の回りの変化は当たり前。かつ、その中で自分も変化させていくのが当たり前の考え方を持っていたのです。
まとめ
ここ迄の下りで、自分の主張は既に分かってもらえたかと思います。
変化の時代を恐れ、変化を不安に感じているのは変化の少ない時代を過ごしてきた大人たちの側なのです。
漠然と変化が大きい。何かしないとまずい。そんな焦燥感に囚われて、実態を見ずにただ焦る。それが我々よりも上の世代なのでしょう。
僕はまだまだ新しい自分を作っていきたい。
もしかしたら、そのチャンスがこの時代の変化の中から生まれてくるかも。今までなら破れなかった殻も、そんな時代だからこそ破れるかも。そんな期待をしています。
そう考えると、ワクワクしてきませんか?
若い世代に負けてる場合じゃないですよ!!