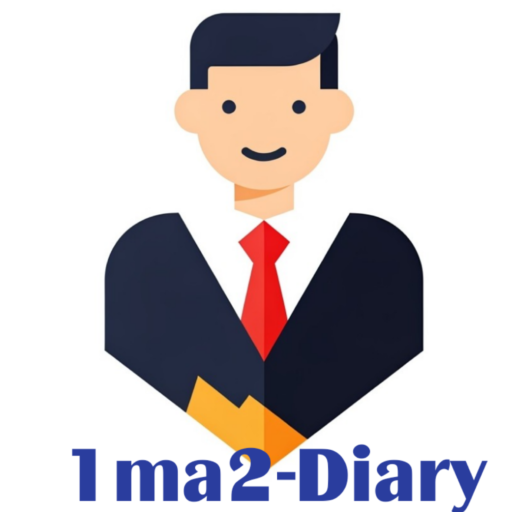【ASD当事者ブログ】結婚20年、定型発達の妻とグレーゾーンの娘と僕 – 異文化コミュニケーションと相互理解の軌跡
はじめに
こんにちは。僕はASD(自閉スペクトラム症)の当事者で、障害者手帳を持っています。そして、結婚して20年になる妻と、僕によく似た娘と暮らしています。妻は、いわゆる「定型発達」と呼ばれるマジョリティ。一方、娘は診断こそ受けていませんが、その特性の出方は僕とそっくりで、おそらくASDのグレーゾーンだろうと感じています。
このブログでは、そんな僕たち家族の日常や、ASD当事者である僕が日々感じていること、特に「コミュニケーション」についてお話ししたいと思います。長く一緒にいる家族であっても、いや、長く一緒にいるからこそ見えてくる「違い」や「壁」。それはまるで「異文化コミュニケーション」のようです。この記事が、同じような境遇の方や、発達障害について知りたい方にとって、何かのヒントになれば幸いです。
僕と妻 – 30年の時を経ても埋まらない溝と、変わらない愛情
妻とは付き合い始めてから30年、結婚して20年が経ちました。人生の半分以上を共に過ごし、誰よりも僕の近くにいてくれる、かけがえのない存在です。僕は妻のことが、本当に大好きです。
しかし、そんな妻との間にも、いまだに「どうして分かってくれないんだろう?」と感じる瞬間があります。ASDの特性として、僕は自分の感情や感覚を言葉にするのが苦手なことがあります。頭の中では分かっていても、それを相手に伝わるように言語化するプロセスが、とても難しい。妻からすれしても、「何でいつも言っているの伝わらないの?」「考えていることが分からない」となるわけです。
これは、どちらが悪いという話ではありません。感覚や思考のプロセスが、根本的に違うのです。よくASDと定型発達の関係は「異文化コミュニケーション」に例えられますが、まさにその通りだと実感しています。文化や言語が違えば、誤解やすれ違いが生まれるのは、ある意味当然のことなのかもしれません。それでも、30年間関係が続いているのは、お互いを理解しようと努力し、そして何より、根底にある愛情があるからだと信じています。
鏡のような娘 – 過去の自分と、未来への願い
僕の娘は、本当に僕によく似ています。特に、ASD的な特性の現れ方がそっくりなのです。物事へのこだわり、興味の偏り、そしてコミュニケーションにおける独特の間合い。診断は受けていませんが、ASDグレーゾーンなのは間違いないでしょう。
そんな娘を見ていると、自分自身の子供時代を思い出します。僕の父親も、今思えば間違いなくASDだったと思います。残念ながら、僕は親から「共感」や「共有」、そして「社会で生きていくための教育」といったものを十分に受けることができませんでした。その結果、対人関係で多くの壁にぶつかり、たくさんの回り道をしてきました。
だからこそ、娘には同じ苦労をさせたくない、という思いがあります。
家族の「翻訳者」として – 妻と娘、それぞれの言い分
妻は、娘の行動や、こだわりに対して、「どうして伝わらないのか。何度言っても出来ないのか。」とよく言います。定型発達の妻からすれば、娘の行動原理は、なかなか受け入れがたいものなのかもしれません。
一方、僕には娘の行動が手に取るように分かります。「あ、今こういう思考回路で、こういう結論に至って、この行動に出たんだな」と。それは、僕自身が同じような思考プロセスを辿ることがあるからです。
今、家庭における僕の役割は、「翻訳者」になることです。妻に対しては、「娘が今こういう理由で、こういう考え方をして、この行動をとっているんだよ」と、娘の思考ロジックを可能な限り言語化して説明します。これは、短期的に妻の混乱やストレスを軽減させるための、対症療法的な側面もあります。
娘へ伝える「マジョリティの世界の歩き方」
同時に、娘に対しても「翻訳」が必要です。例えば、娘が何かをして、周りの人を困らせてしまったり、混乱させてしまったとき。「いま、周りはこう考えていると思うよ。」「なぜ周りの人がそういう思ったのか」を、やはり思考ロジックを追って説明します。「あなたがこういう行動をとったことで、相手はこういう風に受け取って、だから今、こういう感情になっているんだよ」と。
幸い、娘はとても頭の良い子です。説明すれば、定型発達の人がどういう思考回路で物事を捉えるのかを、比較的早く理解してくれます。今後、この経験を積み重ねて、状況から他者の思考や感情を推察する力を、自分自身で養っていってほしいと願っています。
マイノリティが生き抜くために、本当に大切なこと
よく「マイノリティが生きやすい世界を作るべきだ」と言われます。もちろん、それは大前提として非常に重要です。合理的配慮が進み、多様性が認められる社会になることは、僕自身も強く望んでいます。
しかし、それだけでは不十分だと、僕は考えています。特に、今の資本主義社会においては、「マイノリティ側がマジョリティ(多数派)の思考や文化を理解し、そこに配慮する」という視点も、同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に重要なのではないでしょうか。
これは、決して「マイノリティが我慢しろ」という意味ではありません。マジョリティが作り上げた社会のルールや暗黙の了解を理解し、その中でどう立ち回れば、よりスムーズに、よりストレスなく生きていけるかを考える、ということです。それは、ある種の処世術であり、自分自身を守るためのスキルでもあります。
大変で、難しく、時には理不尽に感じることもあります。それでも、マジョリティの思考や感情を理解しようと努めることは、この資本主義の世界で行きていくためには必須だと思うのです。
おわりに
ASD当事者として、夫として、そして父として。僕の毎日は、まさに異文化コミュニケーションの連続です。理解されないことへのもどかしさ、伝えられないことへの悔しさ。それでも、愛する妻と娘と共に、少しでもお互いを理解し合えるよう、日々努力を続けています。
「違い」は、決して悪いことではありません。その違いをどう捉え、どう乗り越えていくか。そこに、家族の、そして個人の成長があるのだと思います。
この記事が、発達障害の当事者の方、そのご家族、そして「コミュニケーションの壁」に悩む全ての方にとって、少しでも共感や気づきを提供できたら嬉しいです。