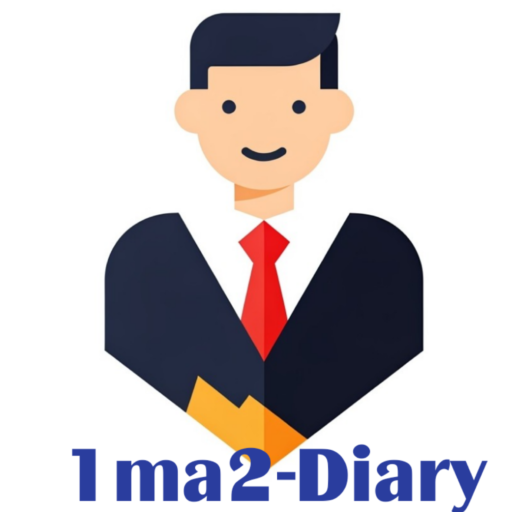【働き方改革の落とし穴?】エンゲージメント低下の真の原因と「1on1」の罠
最近、「働き方改革」という言葉を耳にする機会が非常に増えました。長時間労働を是正し、より生産性の高い働き方を実現しようという動きは、多くの企業で加速しています。
この流れの中で、「個々の業務効率向上」が重要なキーワードとなっています。限られた時間で成果を出すために、社員一人ひとりの生産性をどう高めるか。その解決策の一つとして注目されているのが「エンゲージメント」です。社員の仕事に対するやりがいや意欲、すなわちエンゲージメントを高めることで、集中力を向上させ、結果的に業務効率を上げる、という考え方です。
そして、このエンゲージメントを高める具体的な施策として、「1on1ミーティング」を導入する企業も少なくありません。上司と部下が定期的に1対1で対話し、目標設定や課題解決、キャリア相談などを行うことで、信頼関係を築き、エンゲージメント向上に繋げようという狙いです。
しかし、私の周りでは、特に社歴を重ねた中堅社員から「最近、仕事へのやりがいを感じにくくなった」「意欲が下がっている」といった声を、社内外問わず頻繁に聞くようになりました。
働き方改革で労働時間は減り、エンゲージメント向上のための1on1も導入されている。それなのに、なぜ現場の意欲は低下しているのでしょうか?
一見すると、「エンゲージメントが下がってきたから、1on1などの施策でテコ入れしよう」というのは、理にかなっているように思えます。しかし、私は「エンゲージメントの低下は、根本的な原因ではなく、あくまで表面的な症状の一つに過ぎない」と考えています。そして、この症状だけを見て対策を打つことは、むしろ逆効果となり、業務効率をさらに下げる危険性があると警鐘を鳴らしたいのです。
すエンゲージメント低下は「発熱」と同じ?根本原因を見誤るリスク
例えるなら、インフルエンザにかかって高熱が出たとします。この「発熱」という症状に対して、ひたすら解熱剤で熱を下げようと努力するようなものです。しかし、実際には体内でインフルエンザウイルスと戦うために免疫機能が働き、その結果として熱が出ているわけです。無理に熱を下げようとすれば、かえって免疫の働きを弱めてしまう可能性すらあります。
エンゲージメントの低下もこれと似ています。エンゲージメントが下がっているという「症状」の裏には、もっと根深い原因が隠れていることが多いのです。その根本原因に対処せず、表面的なエンゲージメント向上施策(例えば形骸化した1on1)に注力することは、問題をさらに悪化させかねません。
では、真の原因は何か? ~働き方改革と1on1が生む新たな歪み~
私が考えるエンゲージメント低下、すなわち「やりがい」を下げている要因。それは皮肉なことに、「働き方改革そのものの進め方」と、良かれと思って導入されている「1on1」にあると考えています。
1. 「時間削減」と「安易な人員増」が現場を疲弊させる
まず、長時間労働を是正すること自体は、決して悪いことではありません。これは大前提として同意します。問題なのは、その「施策の進め方」です。
多くの企業では、「一人あたりの労働時間を減らす」ことを目指します。当然、同じ人員構成であれば、組織全体の総労働時間も減少し、結果としてアウトプット(成果)も低下する可能性があります。
ここで経営層が考えがちなのが、「アウトプット量を維持したい。ならば、人を増やせばいい」という、単純な足し算・引き算の発想です。
もし、新たに追加された人員が、入社初日から既存メンバーと同等のパフォーマンスを発揮できる即戦力であれば、この計算は成り立つかもしれません。しかし、現実はどうでしょうか?
特に、企業規模が大きくなればなるほど、その会社独自の文化、業務プロセス、暗黙知といったものが存在します。どんなに優秀な人材を採用したとしても、組織に馴染み、本来の能力を発揮できるようになるまでには、一定の時間と教育が必要です。
さらに深刻なのは、人員増強の「規模」と「スピード」です。
これまで10人のチームに1人新しいメンバーが加わる、といった経験は多くの職場であるでしょう。この場合、既存メンバーがマジョリティであり、新メンバーはマイノリティです。既存メンバーの誰かが中心となり、OJTなどを通じて新メンバーを育成していく体制が自然と機能していました。
しかし、近年の働き方改革に伴う急激な人員増強は、様相が異なります。チームに一度に2人、3人と、これまでにない比率で新しいメンバーが加わるケースが増えています。こうなると、既存メンバーと新メンバーのパワーバランスが変化し、教育・育成の負担は単に人数倍になるのではなく、指数関数的に増大します。
たちが悪いのは、これまで「誰が」「どのように」新人育成を担ってきたのかを、管理職自身が正確に把握していない場合です。この場合、現場で起きている育成負担の急増や、それに伴う既存メンバー(特に中堅層)の疲弊といった課題に気づくことすらできません。有効な対策を打ち出すことは、ほぼ不可能と言えるでしょう。
急激な組織変革は、うまく舵取りできれば組織を活性化させる可能性もあります。しかし、多くの場合、上記のような理由で現場が混乱・疲弊し、結果的に改革が破綻するリスクを孕んでいるのです。
2. 形骸化した「1on1」がエンゲージメントをさらに下げる
エンゲージメント向上の切り札として導入されることの多い1on1ですが、これもまた、運用方法によっては逆効果となり得ます。
そもそも、エンゲージメントが低下している背景には、前述したような「労働時間削減のプレッシャー」と「急な人員増に伴う新人育成の負担増」によって、既存メンバーが疲弊し、本来注力すべき業務に集中できなくなっているという状況が隠れていることが少なくありません。
このような状況下で、「さあ、エンゲージメント向上のために毎週1on1をやりましょう」「議題は部下側で考えて、上司に腹を割って話してください」と言われたら、どう感じるでしょうか?
ただでさえ時間的・精神的な余裕がない部下にとって、1on1のための議題準備や、本音で話すことへのプレッシャーは、さらなる負担でしかありません。これは、エンゲージメントを高めるどころか、むしろ下げる行為になりかねないのです。
さらに問題なのが、1on1の目的や内容を、部下一人ひとりの状況を考慮せずに、画一的に課してしまう管理職の存在です。新しくチームに加わったメンバーと、長年そのチームで貢献してきた中堅メンバーでは、抱えている悩み、直面している困難、求めるサポートは全く異なります。全員に同じ形式、同じ頻度、同じような問いかけで1on1を行おうとしても、うまくいくはずがありません。
では、どうすれば良いのか? ~根本原因への処方箋~
エンゲージメント低下という「症状」に振り回されるのではなく、その「根本原因」に目を向け、対策を打つ必要があります。
多くの日本企業や日本人は、残念ながら急激な環境変化への対応に慣れているとは言えません。構造改革を焦れば焦るほど、現場の混乱は増し、結果的に改革が完了する時期は遅れてしまいます。
改革には痛みが伴うことは、広く知られています。しかし、その痛みを中途半端に緩和しようとしたり、見て見ぬふりをしたりするから、問題がこじれるのです。
まず、「一時的に部署としてのアウトプットが下がることは避けられない」という現実を受け入れる覚悟が必要です。その上で、長期的な視点に立ち、「この部署(チーム)は将来どうなっていたいのか」というビジョンを描き、そこから逆算して具体的なステップを計画します。
そのために最も重要なのが、徹底した現状把握です。それも、トップダウンの視点だけでなく、現場のメンバー一人ひとりの声に耳を傾け、彼らが何に困り、何に疲弊しているのかを正確に把握することです。管理職は、データや報告書だけでなく、現場の実態を肌で感じる努力が求められます。
そして、焦らず、地道な行動を積み重ねること。新しいメンバーの受け入れ体制、教育プログラム、既存メンバーへのサポート、業務プロセスの見直しなど、課題は山積しているかもしれません。しかし、一つひとつ着実に対処していくことが、結果的に最も早く、かつ持続可能な改革に繋がります。
変化の激しい時代だからこそ、地に足をつけた、丁寧な組織運営が求められているのではないでしょうか。
まとめ
働き方改革やエンゲージメント向上への取り組みは、それ自体が間違っているわけではありません。しかし、表面的な「症状」であるエンゲージメント低下に囚われ、安易な人員増強や形骸化した1on1といった対症療法に走ることは、問題をさらに深刻化させる危険があります。
真の課題は、急激な変化に対する組織の対応力の不足や、それに伴う現場の疲弊にある場合が多いのです。
1on1も、その目的や運用方法を誤れば、エンゲージメントを高めるどころか、部下の負担を増やし、意欲を削ぐ結果になりかねません。画一的な導入ではなく、個々のメンバーの状況や課題に合わせた、柔軟で丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
真の業務効率改善とエンゲージメント向上を実現するためには、経営層も管理職も、そして現場のメンバーも、焦らず、現状を正確に把握し、長期的な視点を持って、地道な組織づくりに取り組むことが、今まさに求められていると言えるでしょう。