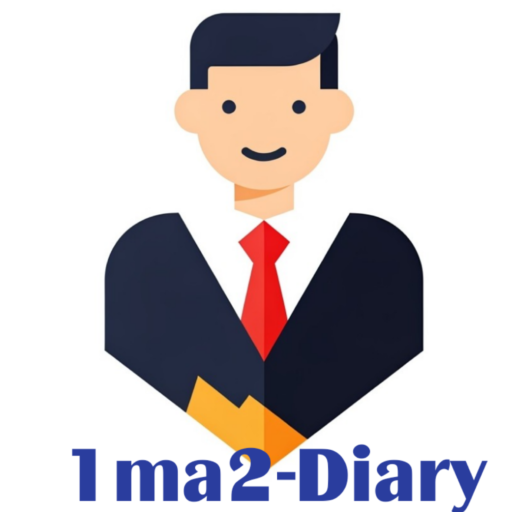【実体験】うつ病・PTSDで休職3年。ASDの私が「疲れの3段階」を知って伝えたい早期休息の重要性
「なんか疲れたな…」そのサイン、見逃さないで。
こんにちは。この記事を読んでくださっているあなたは、もしかしたら過去の私と同じように、心や体の疲れに悩んでいるのかもしれません。
私は3年前にうつ病と診断され、休職しました。原因は、職場のパワハラと、自身のASD(自閉スペクトラム症)の特性による疲れやすさでした。パワハラはPTSD(心的外傷後ストレス障害)も引き起こし、復帰までの道のりは決して平坦ではありませんでした。
診断からリワークプログラムを経て、再び安定して働けるようになるまで、実に1年半もの時間がかかりました。
今、振り返って思うのは、**「もっと早く、自分の疲れに気づいて休んでいれば…」**ということです。
この記事では、私の経験と、回復の過程で大きなヒントとなった心理カウンセラー・下園壮太さんの「疲れの3段階」という考え方、そして**「ちょっと疲れたな」と感じた時点ですぐに休むことの大切さ**についてお伝えしたいと思います。特に、ASDの特性を持つ方には、ぜひ知っていただきたい内容です。
休職に至るまで:気づけなかった「限界」のサイン
休職する前の私は、常に緊張感の中にいました。パワハラによる精神的なストレスに加え、ASDの特性からくる「周囲に合わせなければ」というプレッシャーや、感覚過敏による疲労が積み重なっていたのです。
それでも、「まだ頑張れる」「ここで休むわけにはいかない」と思い込み、自分の心身が発するSOSを無視し続けていました。
- うつ病と診断: ある日突然、糸が切れたように動けなくなり、心療内科を受診。うつ病と診断されました。
- PTSDの併発: パワハラの記憶がフラッシュバックするなど、PTSDの症状にも苦しみました。
- 長い回復期間: 休職開始からリワークまで半年。その後も体調の波があり、完全に回復し、自信を持って働けるようになるまでにはさらに1年を要しました。
「疲れの3段階」との出会い:自分の状態を客観視できた
休職期間中、藁にもすがる思いでメンタルヘルスに関する情報を探す中で、心理カウンセラーの下園壮太さんの考え方に出会いました。
特に、下園さんが提唱する『疲れの3段階』という概念は、当時の私の状態を見事に説明してくれました。
下園さんのブログ(https://ameblo.jp/otonanokokokoro/entry-12755856673.html)や著書『心の疲れをとる技術』によると、疲れは以下のように進行するそうです。
- 第1段階:『疲れたなあ』と感じる段階
- 日常的な疲れ。一晩寝れば回復するレベル。
- 私の経験: この段階で休めていれば、うつ病に至らなかったかもしれません。
- 第2段階:『朝、起きられない』段階
- 疲労が蓄積し、回復が追いつかない。イライラしたり、集中力が落ちたりする。
- 私の経験: 休職直前は、まさにこの状態でした。それでも無理を続けていました。
- 第3段階:『うつ状態』
- 心身ともにエネルギーが枯渇し、何もできなくなる。自己否定感が強まる。
- 私の経験: この段階に至って、ようやく強制的に休まざるを得なくなりました。
この「疲れの3段階」を知ったとき、「ああ、自分は第2段階を通り越して、第3段階まで行ってしまっていたんだ」と、自分の状態を客観的に理解することができました。
なぜ、もっと早く気づけなかったのか?
それは、疲れが進行している最中は、その**「ヤバさ」を実感するのが難しい**からです。「まだ大丈夫」「気のせいだ」と自分に言い聞かせ、無理を重ねてしまう。後から振り返って初めて、「あの時が限界だったんだ」と分かるのです。
「ちょっと疲れたな」は重要なサイン
だからこそ、声を大にして伝えたいのは、「ちょっと疲れたな」「なんか動きたくないな」と感じたら、それは心身からの重要なサインだということです。
その小さなサインを見逃さず、「すぐに」「意識的に」休むことが、深刻な状態に陥るのを防ぐ鍵になります。
- 「週末に休めばいいや」ではなく、その日のうちに休息をとる。
- 短時間でも、意識的にリラックスする時間を作る(深呼吸、ストレッチ、好きな音楽を聴くなど)。
- 睡眠時間をしっかり確保する。
特にASD(発達障害)の人は要注意
ASDの特性を持つ人は、感覚過敏や、変化への弱さ、コミュニケーションにおけるエネルギー消費などから、定型発達の人よりも疲れやすい傾向があります。
また、「疲れ」を自覚するのが苦手だったり、「休む」ことに罪悪感を覚えやすかったりする人もいるかもしれません。
だからこそ、ASDの当事者の方は、意識的に自分の心身の状態を観察し、疲労の初期段階で休息をとる習慣をつけることが非常に重要です。
- 自分の「疲れのサイン」を知る: イライラしやすい、音に過敏になる、特定の考えが頭から離れないなど、自分なりの疲れのサインを把握しましょう。
- 休息をスケジュールに組み込む: 意識しないと休めない場合は、あらかじめ休息時間をスケジュールに入れてしまいましょう。
- 「休む」ことへの許可を自分に出す: 休むことは悪いことではありません。回復し、より良く活動するための大切なプロセスです。
まとめ:自分の心と体を守るために
うつ病とPTSDによる休職という経験は、非常につらいものでした。しかし、その経験と下園壮太さんの「疲れの3段階」という考え方を通して、早期休息の重要性を身をもって学びました。
もしあなたが今、少しでも疲れを感じているなら、どうか無理をしないでください。
「疲れた」と感じたら、休む。
それは、自分自身を守るための、最もシンプルで効果的な方法です。特に、ASDの特性を持つ方は、人一倍、自分の心と体の声に耳を傾け、こまめな休息を心がけてください。
この記事が、少しでもあなたの心と体の健康を守る一助となれば幸いです。
【免責事項】
この記事は、筆者個人の経験に基づいて書かれたものであり、医学的なアドバイスを提供するものではありません。心身の不調を感じる場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。